このレポートは、かたつむりNo.282[2006(平成18)3.19(Sun.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| 境界領域での摩擦の力 |
| 運営委員 道 上 定 |
|
新年早々に「ハテナ」微生物を紹介しました。そのとき口がすべってスパッと割り切れないもの、
分類に収まりきれないもの、アイマイなものが多くて楽しい、などと勝手なことを書きました。
「境界領域・中間領域」や「ニッチ」が目のつけどころで「視床下部」の出番だ、
なんて思ってのことでした。 10数年前のことになりますが、岩波新書『摩擦の世界』を紹介したことがあります。 著者の角田和雄先生は当時、名古屋大学工学部教授。そして科学少年団創設間もない頃から、 私たちと一緒に運営委員として活動指導してくださった中学校の角田理先生のお父様でもあります。 科学者・中谷宇吉郎の「雪の結晶は天から送られた手紙である」ということばに感動し、 寺田寅彦まで導かれて理系に進んだとおっしゃる角田和雄先生が、 このたび『トコトンやさしい摩擦の本』を 「今日からモノ知りシリーズ」の一冊として日刊工業新聞社から出版されました。 現在(財)メカトロニクス技術高度化財団評議員、(財)三豊科学技術振輿協会評議員、工学博士。 「摩擦について面白い話があります。中学の物理の試験に、 もし、この世の中に摩擦というものがなくなったらどうなるのか、記せ。」 という問題を出したのは2002年ノーベル物理学賞受賞者・小柴昌俊先生 (夏季宿泊活動で出かけた岐阜県内に、 ニュートリノをつかまえるためのスーパーカミオカンデを国につくらせた人) が学生時代につとめた中学校講師の時でした。」「この設問の正解は〃白紙答案〃。 摩擦がなければ鉛筆のさきがすべって紙に字が書けないからとのべています。」 (同書10ぺ一ジ)などと面白いことも書いてあります。 目次の中で第2章の「自然の中の摩擦」では動物を人間に変えた摩擦の技術・雷は摩擦から、 地震と津波を起こす摩擦、台風は風と海面との摩擦から、……、などおもしろそうなのがいっぱい! 16の「地滑りや雪崩は摩擦が小さくなると発生する」を見てみましょう。 「砂時計にできる砂山は、その大きさが変わっても形は相似形になります。 砂山に働く重力の斜面方向の成分のために、砂には滑り落ちようとする力が働いています。 …砂時計にできる斜面と水平面との間の角度は45〜50度ですが、 すこし衝撃を加えると崩れて30度ほどの山に変わります。 衝撃によって、一瞬、砂粒同士の間の静摩擦力が動摩擦カに変わるため。 この角度を土木工学では安息角とか休止角と呼んでいます。 …地滑りや崖崩れは摩擦力が小さくなって発生する自然の恐ろしい現象です。 雪崩にも摩擦が関係し、雪の粒、地表との摩擦カの変化で、たとえば鳥や獣の鳴き声でさえも振動が加わると、 それをきっかけとして破壊が始まり、なだれとなるのです。 20の「バクテリアには回転するモータがある」では、 大腸菌やサルモネラ菌のようなバクテリアの鞭毛を回転させるマイクロモータを紹介しています。 摩擦をへらし、回転を円滑にするベアリングでは褶動する材料に同じ材質のものは使いません。 鉄に対して黄銅、青銅、プラスチックスなどを組み合わせます。 同じ材料同士では境界潤滑層が破れたとき焼き付きを起こしやすいのです。 古くから軸受に「ともがね」を使うな、というのはこのことです。 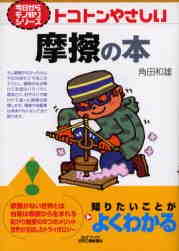 このように摩擦や摩耗、潤滑・転がりなどの全般を扱う工学を「トライボロジー工学」と呼んでいます。
このように摩擦や摩耗、潤滑・転がりなどの全般を扱う工学を「トライボロジー工学」と呼んでいます。聞き慣れない分野なのですが、それもそのはずで機械の動カ伝達技術では古くから問題意識はあったのです。 しかし摩擦をコントロールする技術は信頼性、耐久性、 コストなど商品の差別化に関わることなので高度の企業秘密として一般化していなかった。 同時に物理・化学、材料・機械と、境界領域・中間領域の学術ですから、 体系的に教育の場には出てこなかったのです。 摩擦という・まさに境界領域の問題をテーマとして追及するのは、政治・経済、放送・通信、 保険・金融などと応用というか視野を広げる格好の材料です。 今回の『摩擦の本』は右ぺ一ジに本文、左ぺ一ジは図解となっており、原則見開き1テーマ完結としています。 ひとつ春休みにでも目を通してみたらいかがでしょう。 ¥1、470
|
 戻る
戻る