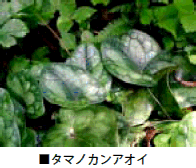「江の島は、いつできたのか」については、科学的に「いつ」と特定するのはむずかしく、
およそ5万年前であろうといわれます(「緑の江の島」p126)。
それ以前、およそ6万5千年前に陸化して
片瀬丘陵の延長で、陸続きであったものが、片瀬海岸のあたり一帯が陥没
()して、島ができたということです。
伝説では、大昔、天地鳴動とともに海中より突出して島ができたと江の島縁起
()にあるのですが、
これも地殻変動による島の成立を示唆しています。
小林政夫先生(藤沢市文化財保護委員)は、以前、神奈川県の第四紀
について詳しく調べた経験をお持ちで、「みどりの江の島」の本では編集長をされています。
ずっと以前、私が江の島の植物を調べていることを知って、あるとき、
「江の島にカンアオイ類は見つかりますか」と聞かれました。
「人の行かない森林の中に分け入っていろいろ調べましたが、見つかりませんでした」と答えますと、
「そうでしょうね、日本のカンアオイ類が成立してから分布するのに、
年数cmの移動速度を考えると、島になってからでは渡ることができないでしょうから」と云われました。
その少し前、岩波新書で。他の植物とともにカンアオイ類の系統進化をわかりやすく解説した前川文夫先生
(
クゲヌマランの新種記載者)の本が出版されて間もなくの頃だったと記憶しています。
カンアオイはギフチョウの食草として知られています。
神奈川県には、ギフチョウの発生地(天然記念物)が津久井にあり、その現場は雑木林です。
藤沢にも、カントウカンアオイとタマノカンアオイの2種があり、私の家にも、40年以上も前、
至るところに自生していた両種を移植したものが元気良く育って、年々広がっていきます。
エンドウ豆ほどもある堅くて大粒の種子は、移動の仕組みは全くなく、
斜面なら転がり落ちることもあるでしょうが、それ以外には動物によって踏み散らされる以外は、
親株から離れることはできません。私の庭でも、この40年間に40〜50cmぐらいしか拡大しませんでした。
株ごとに葉の紋様が微妙に異なりますから、株が分かれたのか、
種からできた別の個体なのかは容易に判別できます。年数cmの移動速度というのは、前川先生の算出です。
カンアオイの生活型()は
「半地中植物」で、しかも常緑です。
同じ生活型をもつ植物には、ヤブラン、ジャノヒゲのほか、ユキワリソウ
()やシュンラン、
エビネなど昔どこにもあったなつかしい山草もふくまれます。
ここで気がつくのは、これらの植物は、
夏緑樹林(落葉広葉樹林、藤沢あたりでは雑木林とケヤキ林がこれにあたる)
と常緑樹林(藤沢ではスギ・ヒノキ植林とシイ・タブ林)の両方によく見られる植物であることです。
40年ほど前まで、どこにも見られたのもうなずけます。
これらの植物群は、もともと自然林内では安定群落の縁辺(ガケや崩壊地、涸れ沢斜面上部などの境界)
に沿って発達するソデ群落の構成種と推定されます。
そして、常緑であることの利点は、初冬()
と早春()の光を効果的に利用できることです。
これらの植物群は、雑木林や植林という、
人類の進出によってもたらされた環境がプラスにはたらいて繁栄したものと思われます。二次林には、
マント群落構成種が多く見られますが、これらの半地中植物はソデ群落の植物で、境界植物として、
人類によって変えられた環境の変化にうまく適応して生活の場を広げてきたと想像されます。
しかし、この半世紀の間に、その環境はさらに変化して、もはや生存がむずかしくなったものと考えられます。
近年、半日陰の緑化材料として、ヤブランやジャノヒゲの園芸品が多く使われりようになりましたが、
それ以外の常緑半地中植物をもっと利用できれば、都市緑化の態様もまた豊かなものになると思われます。
もし、江の島にカンアオイを導入したら、半日陰のグリーンベルトなら、まちがいなく生育すると思われます。
ただし、あくまで植え込み材料としてで、自然の生態系を乱さない配慮が必要となります
|
 戻る
戻る
 戻る
戻る