6月活動の下見で江の島に行きました。江の島のいろいろな「なぞ」に挑戦するという活動ですから、
前もって現場でよく下調べをしておく必要があります。去年、これまでなかった江の島の自然を、
すべてにわたってくわしく解説した本「緑の江の島」ができたので、さっそくこれをテキストとして使います。
以前、理科展が教文センターで行われたとき、「緑の江の島」にのせる資料の一部が展示されました。
その中に植物の写真があり、ヤブソテツの名があるのが気がかりでした。
私は江の島でヤブソテツを見た記憶がないのです。
ちょうど居合わせた菊池先生に「江の島にヤブソテツはあるのですか?」と聞いてみました。
「いくらでもありますよ」との返事におどろいて、写真をよく見たのですが、私にはどう見ても、
オリヅルシダの通常葉
に見えてしまいます。こうなったら現地へ行って、自分の目で確かめるしかありません。
実は私、江の島には何回となく行きましたが、一度もヤブソテツを見たことがないのです。
私の目に入るのは、どれもみなオニヤブソテツばかりでした。
いわれてみれば、江の島にヤブソテツがないわけはないのです。
シダ植物は胞子を空中にとばして繁殖することができますから、
かたつむり272号で紹介したカンアオイとはちがって、
胞子は海を越えてかんたんに島に移動することができます。
120年ほど前、インドネシアのスマトラ島
とジャワ島との間のスンダ海峡に浮かぶクラカタウ島は活火山島で、1883年に大爆発をおこし、
島の大部分が消失し、残ったのは1本の草木もない岩だけでした。
ところがその後十数年たって島が植物に覆われたので、調査隊が調べたところ、
百種を超える植物が生い茂り、中でもシダ植物が多かったそうです。
 「緑の江の島」の本には、「かわいい科学者」の紹介ページ(p8〜9)があって、
片瀬中学の生徒達が調べた54年前の「江の島植物目録」があります。
そこにはオニヤブソテツはありますが、ヤブソテツは載っていません。
また、28年前の「江の島植物園植物目録」にもヤブソテツはありません。
自分で見たことがないのと、この二つの植物目録にもないことから、私は、「江の島にはヤブソテツはない」
ものだと思いこんでいたのです。でも、「ない」と断言できないことは承知していました。
「ある」というのは、1本でも見ていれば「ある」といえますが、「ない」と言い切ることは、
そう簡単にはいえません。さんざんさがして、どうしても見つからなかったとき、
「ないのではないか」というぐらいです。昨年、「緑の江の島」が発行されて、さっそくページを繰ると、
シダの仲間の所に写真がありました。それでも私は、この小さな写真では、
ヤブソテツであると判別することはできませんでした。
「緑の江の島」の本には、「かわいい科学者」の紹介ページ(p8〜9)があって、
片瀬中学の生徒達が調べた54年前の「江の島植物目録」があります。
そこにはオニヤブソテツはありますが、ヤブソテツは載っていません。
また、28年前の「江の島植物園植物目録」にもヤブソテツはありません。
自分で見たことがないのと、この二つの植物目録にもないことから、私は、「江の島にはヤブソテツはない」
ものだと思いこんでいたのです。でも、「ない」と断言できないことは承知していました。
「ある」というのは、1本でも見ていれば「ある」といえますが、「ない」と言い切ることは、
そう簡単にはいえません。さんざんさがして、どうしても見つからなかったとき、
「ないのではないか」というぐらいです。昨年、「緑の江の島」が発行されて、さっそくページを繰ると、
シダの仲間の所に写真がありました。それでも私は、この小さな写真では、
ヤブソテツであると判別することはできませんでした。
 やはり、菊池先生のことばをたよりに、江の島へ行くたびに、ヤブソテツを探し続けるほかはないのだと、
覚悟を決めました。そして、今年、野外観察の下見のために、6月5日に江の島に行くことになり、
目的のひとつに、オニヤブソテツの生えているところを確認してまわる課題がありました。
海から少し離れた山の中の日かげにオニヤブソテツはいくらでも生えているのですが、
ただ、ふつうに道を歩いただけでは、なかなか見つからないものです。
ガケのあるヤブのようなところをさがせばみつかります。海岸を見たあとで、西側から山に入り、
あちこちでオニヤブソテツを見かけましたが、やはり、ヤブソテツは見つかりません。
エスカー乗り場の横から上る道が、辺津宮を出た道に出会う手前から、東海岸に通じる細いガケ沿いの道で、
ようやく葉にまったくつやのないヤブソテツを1株みつけました。
これでようやく江の島のヤブソテツに出会えたわけです。
3年越しの長い長い宝探しもここでやっと終わりを告げました。
江の島植物目録を最初にあらわした「かわいい科学者」片瀬中学校科学部の諸君
から見れば54年越しといえます。「江の島でヤブソテツを見つけた」、
人から見ればこんなとるにたらないようなことでも、植物を研究する私にとっては大きな楽しみになります。
また、この下見では、新しい課題ができました。それは、聖天島のところで、
今では見られなくなったユキヨモギ*かと思われるヨモギに出会ったことです。
秋の開花期に行って、確かめてみたいと思っています。
やはり、菊池先生のことばをたよりに、江の島へ行くたびに、ヤブソテツを探し続けるほかはないのだと、
覚悟を決めました。そして、今年、野外観察の下見のために、6月5日に江の島に行くことになり、
目的のひとつに、オニヤブソテツの生えているところを確認してまわる課題がありました。
海から少し離れた山の中の日かげにオニヤブソテツはいくらでも生えているのですが、
ただ、ふつうに道を歩いただけでは、なかなか見つからないものです。
ガケのあるヤブのようなところをさがせばみつかります。海岸を見たあとで、西側から山に入り、
あちこちでオニヤブソテツを見かけましたが、やはり、ヤブソテツは見つかりません。
エスカー乗り場の横から上る道が、辺津宮を出た道に出会う手前から、東海岸に通じる細いガケ沿いの道で、
ようやく葉にまったくつやのないヤブソテツを1株みつけました。
これでようやく江の島のヤブソテツに出会えたわけです。
3年越しの長い長い宝探しもここでやっと終わりを告げました。
江の島植物目録を最初にあらわした「かわいい科学者」片瀬中学校科学部の諸君
から見れば54年越しといえます。「江の島でヤブソテツを見つけた」、
人から見ればこんなとるにたらないようなことでも、植物を研究する私にとっては大きな楽しみになります。
また、この下見では、新しい課題ができました。それは、聖天島のところで、
今では見られなくなったユキヨモギ*かと思われるヨモギに出会ったことです。
秋の開花期に行って、確かめてみたいと思っています。
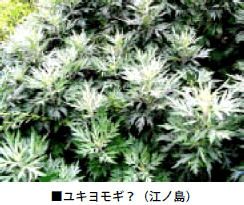 *ふつうのヨモギは、大きく生長した夏の葉は、表面が緑色(裏は白)になるが、
ユキヨモギは、夏の葉の表面も白い蜘蛛毛
で覆われているので、夏でも全草が白い。鎌倉の由比ヶ浜がタイプ・ロカリティ
になっている。
*ふつうのヨモギは、大きく生長した夏の葉は、表面が緑色(裏は白)になるが、
ユキヨモギは、夏の葉の表面も白い蜘蛛毛
で覆われているので、夏でも全草が白い。鎌倉の由比ヶ浜がタイプ・ロカリティ
になっている。
|
 戻る
戻る
 「緑の江の島」の本には、「かわいい科学者」の紹介ページ(p8〜9)があって、
片瀬中学の生徒達が調べた54年前(昭和26年=1951年)の「江の島植物目録」があります。
そこにはオニヤブソテツはありますが、ヤブソテツは載っていません。
また、28年前(昭和52年=1977年)の「江の島植物園植物目録」にもヤブソテツはありません。
自分で見たことがないのと、この二つの植物目録にもないことから、私は、「江の島にはヤブソテツはない」
ものだと思いこんでいたのです。でも、「ない」と断言できないことは承知していました。
「ある」というのは、1本でも見ていれば「ある」といえますが、「ない」と言い切ることは、
そう簡単にはいえません。さんざんさがして、どうしても見つからなかったとき、
「ないのではないか」というぐらいです。昨年、「緑の江の島」が発行されて、さっそくページを繰ると、
シダの仲間の所に写真がありました。それでも私は、この小さな写真では、
ヤブソテツであると判別することはできませんでした。
「緑の江の島」の本には、「かわいい科学者」の紹介ページ(p8〜9)があって、
片瀬中学の生徒達が調べた54年前(昭和26年=1951年)の「江の島植物目録」があります。
そこにはオニヤブソテツはありますが、ヤブソテツは載っていません。
また、28年前(昭和52年=1977年)の「江の島植物園植物目録」にもヤブソテツはありません。
自分で見たことがないのと、この二つの植物目録にもないことから、私は、「江の島にはヤブソテツはない」
ものだと思いこんでいたのです。でも、「ない」と断言できないことは承知していました。
「ある」というのは、1本でも見ていれば「ある」といえますが、「ない」と言い切ることは、
そう簡単にはいえません。さんざんさがして、どうしても見つからなかったとき、
「ないのではないか」というぐらいです。昨年、「緑の江の島」が発行されて、さっそくページを繰ると、
シダの仲間の所に写真がありました。それでも私は、この小さな写真では、
ヤブソテツであると判別することはできませんでした。
 やはり、菊池先生のことばをたよりに、江の島へ行くたびに、ヤブソテツを探し続けるほかはないのだと、
覚悟を決めました。そして、今年、野外観察の下見のために、6月5日に江の島に行くことになり、
目的のひとつに、オニヤブソテツの生えているところを確認してまわる課題がありました。
海から少し離れた山の中の日かげにオニヤブソテツはいくらでも生えているのですが、
ただ、ふつうに道を歩いただけでは、なかなか見つからないものです。
ガケのあるヤブのようなところをさがせばみつかります。海岸を見たあとで、西側から山に入り、
あちこちでオニヤブソテツを見かけましたが、やはり、ヤブソテツは見つかりません。
エスカー乗り場の横から上る道が、辺津宮を出た道に出会う手前から、東海岸に通じる細いガケ沿いの道で、
ようやく葉にまったくつやのないヤブソテツを1株みつけました。
これでようやく江の島のヤブソテツに出会えたわけです。
3年越しの長い長い宝探しもここでやっと終わりを告げました。
江の島植物目録を最初にあらわした「かわいい科学者」片瀬中学校科学部の諸君(私と同年配)
から見れば54年越しといえます。「江の島でヤブソテツを見つけた」、
人から見ればこんなとるにたらないようなことでも、植物を研究する私にとっては大きな楽しみになります。
また、この下見では、新しい課題ができました。それは、聖天島のところで、
今では見られなくなったユキヨモギ*かと思われるヨモギに出会ったことです。
秋の開花期に行って、確かめてみたいと思っています。
やはり、菊池先生のことばをたよりに、江の島へ行くたびに、ヤブソテツを探し続けるほかはないのだと、
覚悟を決めました。そして、今年、野外観察の下見のために、6月5日に江の島に行くことになり、
目的のひとつに、オニヤブソテツの生えているところを確認してまわる課題がありました。
海から少し離れた山の中の日かげにオニヤブソテツはいくらでも生えているのですが、
ただ、ふつうに道を歩いただけでは、なかなか見つからないものです。
ガケのあるヤブのようなところをさがせばみつかります。海岸を見たあとで、西側から山に入り、
あちこちでオニヤブソテツを見かけましたが、やはり、ヤブソテツは見つかりません。
エスカー乗り場の横から上る道が、辺津宮を出た道に出会う手前から、東海岸に通じる細いガケ沿いの道で、
ようやく葉にまったくつやのないヤブソテツを1株みつけました。
これでようやく江の島のヤブソテツに出会えたわけです。
3年越しの長い長い宝探しもここでやっと終わりを告げました。
江の島植物目録を最初にあらわした「かわいい科学者」片瀬中学校科学部の諸君(私と同年配)
から見れば54年越しといえます。「江の島でヤブソテツを見つけた」、
人から見ればこんなとるにたらないようなことでも、植物を研究する私にとっては大きな楽しみになります。
また、この下見では、新しい課題ができました。それは、聖天島のところで、
今では見られなくなったユキヨモギ*かと思われるヨモギに出会ったことです。
秋の開花期に行って、確かめてみたいと思っています。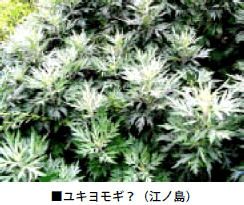 *ふつうのヨモギは、大きく生長した夏の葉は、表面が緑色(裏は白)になるが、
ユキヨモギは、夏の葉の表面も白い蜘蛛毛(くもげ=這うように表面に沿って生える毛)
で覆われているので、夏でも全草が白い。鎌倉の由比ヶ浜がタイプ・ロカリティ
(基準標本採集地)になっている。
*ふつうのヨモギは、大きく生長した夏の葉は、表面が緑色(裏は白)になるが、
ユキヨモギは、夏の葉の表面も白い蜘蛛毛(くもげ=這うように表面に沿って生える毛)
で覆われているので、夏でも全草が白い。鎌倉の由比ヶ浜がタイプ・ロカリティ
(基準標本採集地)になっている。 戻る
戻る