このレポートは、かたつむりNo.263[2004(平成16)11.14(Sun.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| 雷を捕まえる(1) | |||
| 凧→避雷針→ロケット→レーザー | |||
| 運営委員 高 木 茂 行 | |||
|
夏の夕方の一大イベント、雷。今年の夏は異常な暑さのせいか、強烈な雷が何度もやってきた。
皆はすでに知っていることと思うけれど、雷は電気の流れだ。
小さい頃、両親が教えてくれた“雷さま”がいるわけではない。
しかし、あれほど強い光とごう音を耳にすれば、昔の人が“雷さま”を信じるのもうなずける。 雷は、暖かい空気が上昇する時に発生する。 暖かい空気が急上昇すると、周囲の大気との摩擦で静電気が発生する。 下じきと髪の毛を擦ると、下じきに髪の毛がくっ付くのと同じ原理だ。 夏の太陽で暖められた空気は上昇しながら、いたるところで摩擦を起こす。 こうして貯まった多量の電気が、空気中を一度に流れて雷となる。 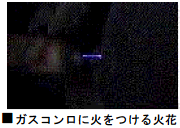 さて、人々が恐れていた雷を科学的に解明、研究しようという挑戦者が現れた。
その先駆けとなったのが、1706年生まれのアメリカ人、ベンジャミン・フランクリン(Benjamin Franklin)だ。
1752年、彼は雷が電気であることを証明するため雷雲に向け凧(たこ)をあげた。
凧糸を伝わった電気が、凧糸の手元につけたカギと手との間で電気の流れとなって光った*。
ガスコンロをつける時に、ぱちぱちと火花が飛んで火がつく。あれと同じような光が見えたはずだ。
今から考えればずいぶん危険な実験だった。
わずかな量の電気しかこなければいいが、雷が凧あるいはフランクリン自身に落ちれば、
彼の命も危なかったはず。絶対に真似をしてはいけない実験だ。
さて、人々が恐れていた雷を科学的に解明、研究しようという挑戦者が現れた。
その先駆けとなったのが、1706年生まれのアメリカ人、ベンジャミン・フランクリン(Benjamin Franklin)だ。
1752年、彼は雷が電気であることを証明するため雷雲に向け凧(たこ)をあげた。
凧糸を伝わった電気が、凧糸の手元につけたカギと手との間で電気の流れとなって光った*。
ガスコンロをつける時に、ぱちぱちと火花が飛んで火がつく。あれと同じような光が見えたはずだ。
今から考えればずいぶん危険な実験だった。
わずかな量の電気しかこなければいいが、雷が凧あるいはフランクリン自身に落ちれば、
彼の命も危なかったはず。絶対に真似をしてはいけない実験だ。
 雷の正体が電気とわかると、雷の研究は急速に進んだ。
雷の被害を避けるための避雷針(ひらいしん)も発明された。
避雷針は大きな建物やマンションの屋上に立てられている金属の棒。
避雷針の先端は建物より高いところにあるから、雷は避雷針に落ちる。
落ちた雷の電気は地面に流れ、建物やマンションが守られるしくみだ。
避雷針に雷を導けるようになると、科学者たちはこれを使って、雷の電気としての性質を計り始めた。
どれくらいの量の電気(電流)が、どれくらいの勢い(電圧)で流れるのか?
雷の電気はどれくらいの時間流れているのか?などなど科学者の研究心は燃え上がる。
雷の正体が電気とわかると、雷の研究は急速に進んだ。
雷の被害を避けるための避雷針(ひらいしん)も発明された。
避雷針は大きな建物やマンションの屋上に立てられている金属の棒。
避雷針の先端は建物より高いところにあるから、雷は避雷針に落ちる。
落ちた雷の電気は地面に流れ、建物やマンションが守られるしくみだ。
避雷針に雷を導けるようになると、科学者たちはこれを使って、雷の電気としての性質を計り始めた。
どれくらいの量の電気(電流)が、どれくらいの勢い(電圧)で流れるのか?
雷の電気はどれくらいの時間流れているのか?などなど科学者の研究心は燃え上がる。しかし、避雷針の実験はとても不便だ。 雷が落ちてくれるかどうは運まかせで、しかもいつ落ちるかわからない。 実験者は落ちる幸運?を望んでひたすら待つことになる。 避雷針を使った実験は、1年に2,3回、悪くすると1回もできずに終わってしまう。 これでは、研究は進まない。思った時に、思った所に雷を落とす方法はないか。 雷の研究を切望する人たちはひたすら考え、ついに革新的な考えに達した。 ロケットに金属ワイヤーを付けて雷雲に向かって飛ばし、ここに雷を落とそうとする方法だ。 避雷針は落ちてくれるのをただ待つしかないけど、急激に上昇するロケットを使えば、 人工的に雷を起こすことができるはずだ。 この革新的なアイデアにフランスのグループが挑み、1965年に世界で始めて人工誘雷に成功した。 この結果に刺激され、日本で始めてロケット誘雷に挑んだのが、 私の大学での恩師である堀井先生を中心とする名古屋大学のグループだ。 堀井先生は、日本でもロケット誘雷を成功させ、雷の研究を加速したいと切望した。 名古屋大学を中心とするメンバーと電力会社に声をかけ、 ロケットを飛ばして雷を測定できる体制を作っていった。 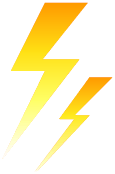 先生の熱意に動かされ、ロケット誘雷の実験が実現した。
最初の実験は、夏の雷をねらって、愛知県の犬山市で行われた。
用意したのは長さ約30cm、直径約10cmのロケット。
実験の準備ができて数日後、期待した雷がやってきた。
人々の熱い思いを集め、1発目のロケットは雷雲に向かって飛んでいった。
しかし、雷はロケットには落ちず、他の場所に大きな光を放って落ちた。
その後もロケットは発射されたが、先生の実験をあざ笑うかのようにまったく関係のない場所に落ち、
初日の実験は失敗に終わった。
その後、雷が来るたび期待を込めロケットを打ち上げたが、空に向かって飛んでいくだけだった。
先生の熱意に動かされ、ロケット誘雷の実験が実現した。
最初の実験は、夏の雷をねらって、愛知県の犬山市で行われた。
用意したのは長さ約30cm、直径約10cmのロケット。
実験の準備ができて数日後、期待した雷がやってきた。
人々の熱い思いを集め、1発目のロケットは雷雲に向かって飛んでいった。
しかし、雷はロケットには落ちず、他の場所に大きな光を放って落ちた。
その後もロケットは発射されたが、先生の実験をあざ笑うかのようにまったく関係のない場所に落ち、
初日の実験は失敗に終わった。
その後、雷が来るたび期待を込めロケットを打ち上げたが、空に向かって飛んでいくだけだった。堀井先生は、実験が失敗したことに失望した。 実験を始めるため、たくさん人々に雷を落とせると説明した。 これを信じて協力してくれた人達には合わせる顔がなかった。 そして何よりも困ったことに、今回の実験でその年に研究に使えるお金をほぼ使いきっていた。 今後どうしたらよいのか、先生は見当もつかなかった(続く)
|
 戻る
戻る