このレポートは、かたつむりNo.264[2004(平成16)12.12(Sun.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| 雷を捕まえる(2) |
| 凧→避雷針→ロケット→レーザー |
| 運営委員 高 木 茂 行 |
夏の実験で、雷を落とすことに失敗した堀井先生は、協力してくれた人々を集めて反省会を開いた。
ここで、誘雷に成功しているフランスの実験との違いを詳しく調べた。その結果、フランスの実験では、
雷雲の位置が低いこと、雷の発生頻度が高いことが分かった。このまま、犬山市で夏の雷をねらっても、
誘雷できないのではという感触だった。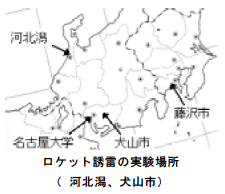 そんな時、北陸に住んでいる人から耳よりな話を聞いた。北陸では、冬になると海岸沿で雷が多発する。
海岸の少し高いところにいると、周囲全体が霧(きり)に包まれて雷雲の中にいるようだ。
藤沢に住んでいる僕らには、雷は夏というイメージがあるが、北陸では冬に雷が多発する。
冬の北陸は寒く、地面は凍りついたように冷たい。一方で、海水は凍らずに地面よりずっと暖かい。
日本海の海面を渡った空気は、地面の空気より暖かいため陸地で急速に上昇して雷を発生させる。
そんな時、北陸に住んでいる人から耳よりな話を聞いた。北陸では、冬になると海岸沿で雷が多発する。
海岸の少し高いところにいると、周囲全体が霧(きり)に包まれて雷雲の中にいるようだ。
藤沢に住んでいる僕らには、雷は夏というイメージがあるが、北陸では冬に雷が多発する。
冬の北陸は寒く、地面は凍りついたように冷たい。一方で、海水は凍らずに地面よりずっと暖かい。
日本海の海面を渡った空気は、地面の空気より暖かいため陸地で急速に上昇して雷を発生させる。これは、先生が失敗の原因と考えていた2つを解決してくれそうだった。雷の雲は低いし、 海からの流れに乗って雷は次々発生する。しかし、先生は迷った。雷の実験は野外だ。 残ったお金はわずかだから、実験するための建物にお金はかけられない。たぶん、簡単なプレハブになる。 北陸の気候を考えると、突き刺すような寒が頭に浮かんだ。それに機材の運搬も大変だ。 名古屋大学から犬山市ならすぐだから何度も行き来できるが、遠い北陸では、 実験する人はそう簡単に戻っては来られない。悩みは尽きなかったが、やるしかなかった。 このまま成功しないと、研究するためのお金は大幅に削られる。苦しい決断だった。 実験に選ばれたのは、石川県金沢市の河北潟だった。ここは河北湖を埋め立てた原野が広がり、 ロケットをいくら打ち上げても、人家への影響のないところだった。 実験用のプレハブの建物ができ、寝泊りする寝床が作られた。ステンレスの工作材を使った簡単なもので、 その上に湿った布団が置かれた。プレハブの中にはストーブが置かれたが、室内とはいえ、 真冬の藤沢の野外にいるようなものだった。 1977年の12月22日、プレハブに残っていたのは、 堀井先生と誘雷実験を続けてきた小西さんと長縄さんだった。夕方になり、 プレハブの中はしんしんと冷えてきた。雷が何時きてもおかしくない状況ではあったが、 二人は日本酒を飲んでいた。そうしないと、寒さで身体が持たなかった。夏は1ヶ月にもわたり、 実験したのに一度も誘雷できなかった。今度もダメなのではと、二人とも黙り込んでいた。 そこに、堀井先生が戻って来られた。先生は、アメリカの学会に誘雷の報告を聞きに行っていたのだ。 その先生からは、弱気の発言しか出なかった。先生も加わってお酒を飲み、3人ともうとうとし始めていた。 その時、雷の接近を知らせる電界計が上がり始めたのに先生が気付いた。 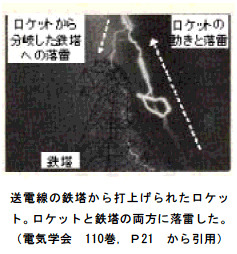 「小西君、電界が上がってきた。ロケットは発射できるのか」
「小西君、電界が上がってきた。ロケットは発射できるのか」「はい、先生」 3人とも一気に酔(よい)はさめ、実験に夢中になった。 すぐに、最初のロケットが音と立てて飛んでいったが、何の反応もなかった。 「電界は、今どれくらいだ」 「これから読みます」 「いいから、発射して」 2発目のロケットが発射された。その瞬間、周りに猛烈な音が響いた。 3人とも何が起きたか分からず、目を合わせた。 「雷が落ちた証拠は残っていないか」 先生が叫んだ。雷を測定する装置には、雷の電気が流れたことを示す跡がかすかに残っていた。 1977年12月22日、日本で初めてロケット誘雷に成功した日だった。 その後、ロケット誘雷の実験は順調に進み、200回以上の誘雷に成功した。雷を流そうとする電圧、 雷を流れる電流、雷の持続時間などが次々と測定されていった。得られた結果は学会で発表され、 多くの研究者を刺激した。そして、別の方法で雷を導こうという人々が現れた。 大阪大学でレーザーを研究しているグループだった(続く)
|
 戻る
戻る