このレポートは、かたつむりNo.266[2005(平成17)1.8(Sat.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| 雷を捕まえる(3) | ||
| 凧→避雷針→ロケット→レーザー | ||
| 運営委員 高 木 茂 行 | ||
ロケットによる雷の実験は、短期間に多くの雷を落とすことができ、
まとまったデータを集中的に集めることができた。しかしながら、
ロケット誘雷は火薬を使うため法律上の規制が多く、いつでもどこでも打ち上げるわけにはいかない。
また、ロケット自体は発射で粉々になるが、誘雷しない時にはワイヤーが落ちてくる可能性もあった。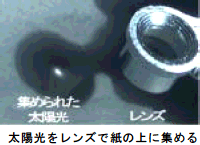 誘雷するための新たに仕組みとして考えられたのがレーザーであった。レーザーを一言で言うと、
太陽や蛍光灯などに比べ桁違(けたちが)いに強い光だ。レンズを使うと太陽の光を集めることができ、
大きなレンズだと紙を焦がすことも出来る。(だから、絶対レンズで太陽を見てはいけない)
しかし、レーザーの光を集めると、厚み10cm以上の鉄板を切ることもできる。
ゴジラやスターウォーズなどの映画に出てくる光線銃の正体はこれだ。
今ではレーザーは鉄板を切ったり、細い穴を開けたりするのに使われていて、
皆が良く知っている自動車のサンルーフ窓もレーザーで開けられている。
誘雷するための新たに仕組みとして考えられたのがレーザーであった。レーザーを一言で言うと、
太陽や蛍光灯などに比べ桁違(けたちが)いに強い光だ。レンズを使うと太陽の光を集めることができ、
大きなレンズだと紙を焦がすことも出来る。(だから、絶対レンズで太陽を見てはいけない)
しかし、レーザーの光を集めると、厚み10cm以上の鉄板を切ることもできる。
ゴジラやスターウォーズなどの映画に出てくる光線銃の正体はこれだ。
今ではレーザーは鉄板を切ったり、細い穴を開けたりするのに使われていて、
皆が良く知っている自動車のサンルーフ窓もレーザーで開けられている。このような強いレーザーをレンズで集めると、レーザーで空気が瞬間的に温められ、 雷と良く似た状態になる(レーザープラズマ*)。空気に電気が流れる状態だ。 雷雲に向かってレーザー放出すれば、このレーザープラズマに導かれ、雷を誘導(ゆうどう)できる。 ロケットのような火薬も要らなければ、ワイヤーもいらない。 レーザー誘雷に最初に挑んだのは、アメリカの空軍研究所だった。 1979年に、山頂からレーザーを放出して500m上空で数メートルに及ぶレーザープラズマを作ったが、 誘雷には至らなかった。日本では、1980年頃から室内での実験が行われ、 1994年から1999年にかけて室外での実験が行われた。 実験は、ロケット誘雷と同じように冬の雷をねらって北陸の福井県美浜町の嶽山で行われた。 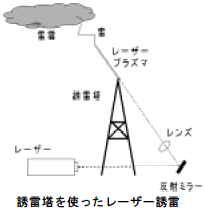 この時、レーザーで雷を導くための工夫が加えられた。
ロケット誘雷ではロケットの高さが地上70〜100mに達した時に限って成功している。
しかし、レーザープラズマができるとこの部分で光エネルギーが吸収され、その先にレーザーが伝わらない。
また、長い距離にわたり光を絞るレンズを作るのもむずかし。
このため、レーザープラズマの長さは数10mが限界で、
ロケット誘雷で必要とされた70〜100mのレーザープラズマを作ることは困難だった。
そこで、雷を落とすために高さ50mの誘雷塔(ゆうらいとう)を使い、
この先にレーザープラズマを作る方法が取られた。
この時、レーザーで雷を導くための工夫が加えられた。
ロケット誘雷ではロケットの高さが地上70〜100mに達した時に限って成功している。
しかし、レーザープラズマができるとこの部分で光エネルギーが吸収され、その先にレーザーが伝わらない。
また、長い距離にわたり光を絞るレンズを作るのもむずかし。
このため、レーザープラズマの長さは数10mが限界で、
ロケット誘雷で必要とされた70〜100mのレーザープラズマを作ることは困難だった。
そこで、雷を落とすために高さ50mの誘雷塔(ゆうらいとう)を使い、
この先にレーザープラズマを作る方法が取られた。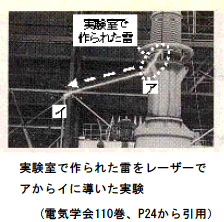 こうした検討を行い、1994年には始めてレーザーを室外に設置して、
レーザーを雷雲に向かって発射する実験を行った。
95年には誘雷塔の先端に約20mのレーザープラズマを作るのに成功した。
96、97年には雷が近づいた時にタイミングを合わせてレーザーを発射できる仕組みを作り、
98年には実際に雷を誘導する実験に望んだ。
こうして、1999年1月29日にはレーザープラズマから雷の一部が成長する様子が観測され、
ついに2月11日にはレーザーによる誘雷に成功した。
1994年に室外実験を始めてから、4年目以上の月日が流れていた。
こうした検討を行い、1994年には始めてレーザーを室外に設置して、
レーザーを雷雲に向かって発射する実験を行った。
95年には誘雷塔の先端に約20mのレーザープラズマを作るのに成功した。
96、97年には雷が近づいた時にタイミングを合わせてレーザーを発射できる仕組みを作り、
98年には実際に雷を誘導する実験に望んだ。
こうして、1999年1月29日にはレーザープラズマから雷の一部が成長する様子が観測され、
ついに2月11日にはレーザーによる誘雷に成功した。
1994年に室外実験を始めてから、4年目以上の月日が流れていた。これまで、3回にわたり日本での雷の研究に関する新しい試みを書いた。 これを読んで皆はどう思っただろうか? いろんな感想をもったかも知れないが、 科学的に新しい試みに失敗は付きものだということ、 新しい試みではそれまで他人がやった実験結果を参考にしていることには、誰もが気付いただろう。 避雷針は雷が電気とわかったことで作られたし、 ベンジャミンの凧の実験をヒントにロケットに雷を落とす方法が考えられた。 ロケット誘雷が冬の実験で成功したことをもとに、レーザー誘雷も冬の雷で実験が行われている。 学校で習う理科の授業は、こうした新しいことにチャレンジするために最も重要な内容だ。 レーザー誘雷でレンズによりレーザーを集める方法も、学校でやる太陽光をレンズで集める実験の応用だ。 しっかり勉強して、いずれは周囲をあっと驚かせるような新しい何かに挑戦して欲しい。
|
 戻る
戻る