このレポートは、かたつむりNo.270[2005(平成17)4.17(Sun.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| 20XX年 町から電球が消える日(1) |
| 運営委員 高 木 茂 行 |
|
このタイトルを読んで、皆は何を思っただろうか。
人類が環境を破壊して今のような生活ができなくなり、町から明かりがなくなると考えた人もいるだろう。
そして、中には高木運営委員が興味を引くためにデタラメを並べていると疑った人もいるだろう。
しかし、これはかなり近い将来、早ければ5年もすれば起きるかも知れない現実なのだ。 もう一度タイトルを見て欲しい消えるのは電球であり明かりではない何が起きるのか? 一言でいえば、街の電球がLED*に置き換わってしまうのだ。 LEDは去年も今年も2月の電気工作で使った豆電球のような物。電池につなげは赤や緑に光る。 同じ電気を使っても豆電球に比べ2倍以上も明るい。たかが2倍と思わないで欲しい。 家庭で使われる電気が半分になれば、日本全体ではすごい量の省エネになる。豆電球や照明用の電球は、 1~3年でフィラメントが切れて交換する必要があるけど、LEDは10年以上使うこともできる。 このLED、ここ数十年程で大きな進歩をとげた。 一つはとても明るくなったこと、そしてもう一つは青色のLEDが作られたことだ。 もともとLEDは強い光が得られず、電気製品の動きを示す目的に使われていた。 例えば、テレビやパソコンのスイッチを入れるとLEDが緑色に光り動いていることを示すといった具合だ。 それが少しずつ明るくなって、今では交通信号、車のライト、大きな表示灯に使われている。 藤沢市内のバスや電車も、行き先表示が白地に黒のシートからオレンジ色のLEDに変わっている。  こんなに身近になったLEDについて皆と一緒に考えていきたい。
今回のお話は、「LEDと電球はどこが違いなぜ光るのだろうか?」だ。
図1は、電球(左)とLED(右)の写真。
電球はガラスの中に電気の流れにくい線(フィラメント)が入っていて、
これに電気を流すと線が熱くなり光を放つ。
基本的には電気ストーブやオーブントースターと同じようなもの。
熱いものからは光が出る性質があり、電気ストーブにスイッチを入れると赤く光るのと同じ仕組み。
こんなに身近になったLEDについて皆と一緒に考えていきたい。
今回のお話は、「LEDと電球はどこが違いなぜ光るのだろうか?」だ。
図1は、電球(左)とLED(右)の写真。
電球はガラスの中に電気の流れにくい線(フィラメント)が入っていて、
これに電気を流すと線が熱くなり光を放つ。
基本的には電気ストーブやオーブントースターと同じようなもの。
熱いものからは光が出る性質があり、電気ストーブにスイッチを入れると赤く光るのと同じ仕組み。次にLED。ところで、これまでの電気工作でLEDの電池へのつなぎ方を間違えた時は、 どうなったかおぼえているだろうか?そう、まったく光らないのだ。 これは豆電球と大きな違い。 LEDというのはプラスの電気の多い物と、マイナスの電気の多い物を**、 図2の①ようにつなぎ合わせている。プラスとマイナスの電気というのは、 電池のプラスとマイナスに対応するようなものと考えてもらえばいい。 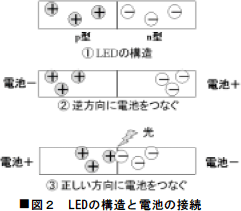 ここで、図2の②のように、間違ってつなぐと、プラスの電気は電池のマイナス側に、
マイナスの電気は電池のプラス側に移動して電気は流れない。ところが、図2の③のように正しくつなぐと、
プラスの電気は電池のプラスに押され真中に向かい、同じようにマイナスの電気も真中に向かう。
そして、真中でプラスとマイナスの電気が出会って光を放つ。
野球のボールをグローブで受け止めると大きな音が出るが、音の代わりに光が出ると思ってもらえばいい。
ここで、図2の②のように、間違ってつなぐと、プラスの電気は電池のマイナス側に、
マイナスの電気は電池のプラス側に移動して電気は流れない。ところが、図2の③のように正しくつなぐと、
プラスの電気は電池のプラスに押され真中に向かい、同じようにマイナスの電気も真中に向かう。
そして、真中でプラスとマイナスの電気が出会って光を放つ。
野球のボールをグローブで受け止めると大きな音が出るが、音の代わりに光が出ると思ってもらえばいい。さて、LEDがどうして光るかなんとなく理解できたと思うけど、 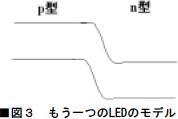 図2の①でプラスの電気とマイナスの電気をつなぎ合わせた状態を、
電気の専門家は図3のような2組の平行線で書く。これは、一体なんだ??と思った人。
LEDをどうやって明るくしてきたかに興味のある人は、「20XX年 町から電球が消える日(2)」
をお楽しみに。おどろくことに、今の1個のLEDは、30年前の100個のLEDと同じ明るさになっている。
図2の①でプラスの電気とマイナスの電気をつなぎ合わせた状態を、
電気の専門家は図3のような2組の平行線で書く。これは、一体なんだ??と思った人。
LEDをどうやって明るくしてきたかに興味のある人は、「20XX年 町から電球が消える日(2)」
をお楽しみに。おどろくことに、今の1個のLEDは、30年前の100個のLEDと同じ明るさになっている。
|
 戻る
戻る