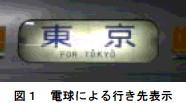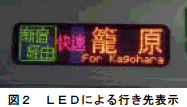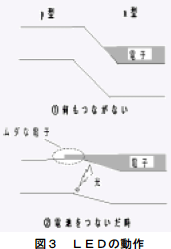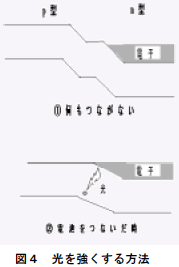このレポートは、かたつむりNo.271[2005(平成17)5.15(Sun.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| 20XX年 町から電球が消える日(2) | ||||
| 運営委員 高 木 茂 行 | ||||
さて、初めの頃のLEDは、電球と比べるととても弱かった。 しかし、30年が経過して100倍近く明るくなり、電球と同じくらいになった。 では、どうやって明るくしていったのだろう。 まず思いつくのが、LEDから出てくる光を全部集めることだ。 LEDの後ろと横に鏡を置けば、それらの方向の光も取り出すことが出来る。 懐中電灯の電球の周りにある円錐の鏡と同じような考えだ。 この方法では、前、後ろ、右、左の4方向の光を前に集めるから、 上手くいけば光は4倍強くなるけど、100倍は無理だ。 そこで登場するのが(1)で紹介した図3のような2組の平行線の図だ。 これは、LEDの動きを実に上手く表す「モデル」だ。まず、図3の①が電池をつながない状態。 上下の線の位置は、電圧の高さを示している。電圧というのは乾電池に書いてある1.5V (ボルト)という値で、どれくらい電気を流す力があるかを示す値。 乾電池の場合、飛び出したプラスは平らなマイナスに対し、1.5Vの力で電気を流せる。 図3の①でP型はプラスなので高い位置にあり、n型はマイナスなので低い位置にある。 n型の上にあるグレイの部分にはマイナスを持った電子が溜まっている。 実は電気が流れるというのは、この電子が移動すること。 図3の①ではマイナスの電子はプラスのP型に行きたいのだが、 P型の電圧が高いため移動できない。 ここに電池をつなぐと、図3の②のように電圧の差が小さくなり、電子がP型に流れ、 P型のプラスと結びついて光を放つこの状態は、 図3の②では電子がP型の上から下に落ちることで表す。 少し荒っぽいたとえをすると、P型という部屋とn型という部屋があり、この間に壁がある。 この壁が低くなるとn型の部屋にいた好奇心の強い人が壁を飛び越え、 P型の部屋に落ちて「痛い」と叫んでいるようなものだ。この「痛い」が、光だと思えばいい。 図3の②で電子の一部は、P型の方に広がっている。この電子は光を出さず、むだになっている。 P型に電子がはみ出さないようにすれば、その分が光に変わり、強い光が得られる。 では、どうすればいいのか。図4の①のように中間にもう一つの壁を作ってやり、 図4の②のように電子が漏れ出さないようにすればいい。 そんなに思い通りになるのだろうか?こんな頼りない図で考えたことが、 本当になるのだろうか?・・・ 疑いたくなるもなるけど、この考えに従ってLEDを作ると、 予想通り普通のLEDより強い光がでる。この方式のLEDは、ダブルヘテロ接合方式と呼ばれ、 実際の製品として売られている。 さらに、図3を使って「量子井戸(りょうしいど)接合」という方式も考えられ、 LEDの光を強くすることに成功している。図3を使うとLEDの動作が理解でき、 光をたくさん出す方法も考えることができる。こうした仕組みは「モデル」と呼ばれている。 小学校では習う「てこ」は、支点、力点、作用点で「てこ」のモデルを作っていて、 それは大きさの違うすべてに共通だ。LEDのモデルが理解できれば多くのことがわかるように、 理科の勉強ではモデルの意味をしっかり理解することがとても大切だ。 さて、モデルを使いながらLEDの光は100倍にまで強くなった。そして、 一部のLEDは電球に代わるようになったが、家庭の灯りとして使うには大きな問題があった。 青い光、白い光のLEDが作れなかったことだ。 しかし「青い光のLEDは出来ない」というという考えも、この10年で完全にに打ち破られた。 「町から電球が消える日(3)」はその話だ。 |
 戻る
戻る