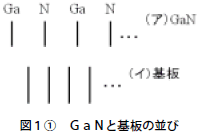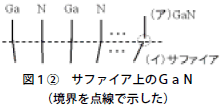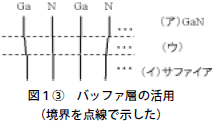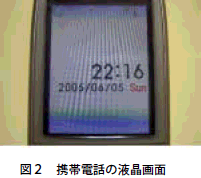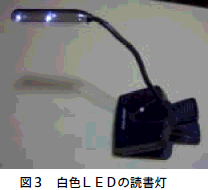偙偺儗億乕僩偼丄偐偨偮傓傝No.272[2005(暯惉17)6.12(Sun.)]偵宖嵹偝傟傑偟偨
 栠傞
栠傞
| 俀侽XX擭丂挰偐傜揹媴偑徚偊傞擔乮俁乯 | |||||
| 塣塩埾堳丂崅丂栘丂栁丂峴 | |||||
|
丂巹偑妛惗偩偭偨崰丄戝妛偱俴俤俢偺庼嬈傪庴偗偨丅愭惗偼妛惗偵岦偐偭偰丄 乽愒傗墿怓偺俴俤俢偼偱偒偰偄傑偡偑丄惵偄俴俤俢偼偱偒側偄偱偟傚偆乿 偲尵偭偨丅偦偺帪丄俴俤俢偵偼嫽枴偑側偐偭偨偐傜丄愭惗偺尵梩傪慺捈偵庴偗擖傟丄 壗偺媈栤傕帩偨側偐偭偨丅偟偐偟丄栺俀侽擭偺帪偑宱夁偟丄 惵偄俴俤俢偼挰偺偁偪偙偪偱尒傜傟傞傛偆偵側偭偨丅
丂傢偐傝堈偔偡傞偨傔丄俀庬椶偺屌傔偺恓嬥偱峫偊偰傒傛偆丅 暆偺峀偄娫妘偺恓嬥乮傾乯偲嵶偄娫妘偺恓嬥乮僀乯偺俀庬椶偑丄恾侾嘆偺傛偆偵墶偵暲傫偱偄偨偲偡傞丅 乮傾乯偑俧倎俶偱丄乮僀乯偑婎斅偲偡傞偲丄摉慠偺偙偲側偑傜乮傾乯偲乮僀乯偼偮側偘側偄丅 側傫偲偐偮側偖偵偼丄偳偆偟偨傜椙偄偺偩傠偆丠丂傑偢丄巚偄偮偔偺偼弌棃傞偩偗暆偺嬤偄丄 乮傾乯偲乮僀乯傪慖傇偙偲偩丅偦偙偱丄乮傾乯偵嬤偄婎斅偲偟偰僒僼傽僀傾 乮偁偺曮愇偺僒僼傽僀傾偲摨偠偩偗偳丄恖岺偺僒僼傽僀傾乯偑慖偽傟偨丅 幚嵺偵僒僼傽僀傾偺忋偵俧倎俶傪嶌傞幚尡傪偟偰傒傞偲丄俧倎俶偺枌偼晹暘揑偵億僣億僣偲僑儅忬偵側傝丄 堦柺偵峀偑傞枌偼弌棃側偐偭偨丅恾侾嘇偺傛偆偵彮偟偖傜偄側傜曄宍偟偰偮側偑傞偗偳丄 挿偔側傞偲偄偢傟偳偙偐偱夡傟傞丅偙偺偨傔丄彫偝側屌傑傝偲側偭偰偟傑偭偨丅 丂傎偐偵曽朄偼柍偄偺偩傠偆偐丠偙偙偱丄乮傾乯偲乮僀乯偺暆偺拞娫偺暆傪帩偭偨恓嬥乮僂乯 傪擖傟偨傜偳偆偩傠偆丅恾侾嘊偺傛偆偵乮僂乯偑乮傾乯偲乮僀乯傪嫶搉偟丄 忋庤偔偮側偑傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丠偄傠傫側嵽椏偲偄傠傫側忦審傪慻傒崌傢偣丄 傗偭偲婎斅偺忋偺堦柺偵峀偑傞俧倎俶枌傪嶌傞偺偵惉岟偟偨丅崱偱偼丄乮僂乯偼僶僢僼傽憌偲屇偽傟偰偄傞丅
丂椺偊偽丄実懷揹榖偼僶僢僥儕乕偱摦偄偰偄傞偐傜丄堦夞偺廩揹偱挿帩偪偝偣傞偵偼丄 恾俀偺傛偆側夋柺偱巊偆揹婥偺検傪尭傜偟偨曽偑椙偄丅 俴俤俢偺曽偑摨偠岝傪弌偡偵傕彮側偄揹婥偱偡傓偙偲偐傜丄 嵟嬤偺実懷揹榖偺夋柺偱偼揹媴偺戙傢傝偵敀怓俴俤俢偑巊傢傟偰偄傞丅 傑偨丄怮傞帪偵杮傪撉傓偨傔偺恾俁偺傛偆側撉彂摂偱傕丄揹媴偺戙傢傝偵俴俤俢偑巊傢傟偰偄傞丅 俴俤俢偵偡傞偙偲偱丄揹抮偱傕挿偄娫巊偆偙偲偑偱偒丄帩偪塣傃偵傕曋棙偩丅 丂偙偆偟偰丄俴俤俢偼彮偟偯偮揹媴偵抲偒姺傢偭偰偄傞丅 廫擭慜偵僇儊儔偲偄偊偽丄僼傿儖儉幃偑庡棳偩偭偨偑丄偄傑偱偼僨僕僇儊偑庡棳偵側偭偰偄傞丅 壗擭傕偡傟偽丄俴俤俢偑揹媴偵抲偒姺傢傝丄偙偺暥復偺僞僀僩儖偺傛偆偵乽挰偐傜揹媴偑徚偊傞乿偐傕偟傟側偄丅 丂偝偰丄偙偙傑偱偼堦斒揑側榖丅崅栘塣塩埾堳偺斀徣傪嵟屻偵丅 丂傕偟丄戝妛偺帪偵丄愭惗偵乽偳偆偟偰惵偄俴俤俢偼偱偒側偄偺偱偡偐丠乿偲幙栤傪偟偰偄偨傜丅 偁傞偄偼丄俧倎俶偺枌傪嶌傞傛偆側幚尡傪妛惗偺帪偵傗偭偨偐傕偟傟側偄丅 偦偆偡傟偽丄壗傜偐偺宍偱惵怓俴俤俢傪嶌傞偙偲偵実傢傟偨偐傕偟傟側偄丅 壢妛偱偼乽偳偆偟偰偩傠偆乿偲偄偆媈栤傪帩偮偙偲廳梫偩偲丄惵怓俴俤俢傪尒傞偨傃偵斀徣偝偣傜傟傞丅 |
 栠傞
栠傞