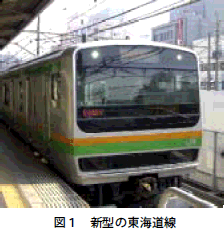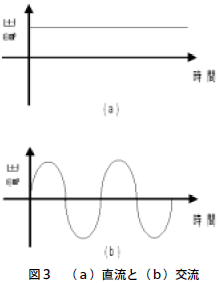このレポートは、かたつむりNo.277[2005(平成17)11.13(Sun.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| ありがとう!110系東海道線(湘南電車) | |||
| 運営委員 高 木 茂 行 | |||
昨年の10月に東海道線では、大幅なダイヤ改正が行われた。東海道線から直通で渋谷、新宿、
池袋方面に行ける湘南新宿ラインが大幅に増え、
昼間は藤沢駅から30分間隔で運転されるようになった。
このダイヤ改正にともない、もう一つの大きな変化が起きた。 東海道線に図1のような新型車両が導入された。オレンジと緑で塗り分けられたこれまでの車両に対し、 金属色のボディにオレンジと緑のラインが入った新しい車両だ。古い車両は110系という型番がつけられ、 別名湘南電車とも呼ばれている(図2)。 これに対して、新しい車両はE230系という型番がつけられている。 これらの番号は、扉の横で車体の下の方に書かれている。 ところで、この110系東海道線、最近はあまり見かけなくなっている。 実は、来年の1〜2月にはすべて新型車両に置き換わってしまう。この電車に愛着を感じている人は、 それまでに何度も乗っておくことをお勧めする。 さて、この2種類の東海道線は同じ線路の上を走っているが、電車を動かす仕組みはまったく違う。 それを示すのが電車に車体に書かれた番号。110系の100、E230系の200という数字だ。 110系車両には直流モータが、E230系には交流モータが使われている。 直流モータを使った方式では、電車を動かし始める時、およそ半分の電気を無駄にしている。 これに対して、交流モータでは、無駄になる電気は電車を動かすのに必要な電気の1/10以下という優れもの。 新しい東海道線は、環境にやさしいエコ車両なのだ。 直流モータと交流モータを使った電車の仕組みについて2回に分けて説明する。まず、最初に直流と交流。 直流では図3に示すように何時も一定の電圧がかかっているのに対し、交流では電圧が時間とともに変化する。 直流の代表は電池。電池はいつも一方がプラス、他方がマイナス。 電池で動く懐中電灯やデジカメは直流で動いている。これに対して交流の代表は家庭のコンセント。 コンセントにプラグをさして使う扇風機、掃除機、洗濯機には交流モータが使われている。 ただし、携帯電話の充電器やパソコンはコンセントを使っているが、 実際には直流が使われるのでコンセントからの交流を直流に変えて使っている。 携帯電話の充電やパソコンで、コンセントにつなぐ黒い箱はアダプターと呼ばれ、直流を作るためのもの。 この15年ほどで半導体と呼ばれる素子が大きく進歩し、直流から交流、 交流から直流に電気の性質を変えることがとても簡単になった。 こうした電気エネルギーを扱う分野はパワーエレクトロニクスと呼ばれている。 東海道線の架線には直流がきているが、 新しいE230系の電車ではパワーエレクトロニクスを使って直流を交流に変えてモータを動かしている。 パワーエレクトロニクスは、電車だけでなく自動車にも広がっている。 最近話題になっているハイブリッド自動車や燃料電池自動車が動くのも、 電車を交流モータで動かすしくみに近い。 話を東海道線に戻して。では、どうやって直流を交流に変えているのか。 直流モータと交流モータとはどこが違うのか。次回の「かたつむり」をお楽しみに。 |
 戻る
戻る