このレポートは、かたつむりNo.278[2005(平成17)12.3(Sat.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| ありがとう!110系東海道線(湘南電車) |
| 運営委員 高 木 茂 行 |
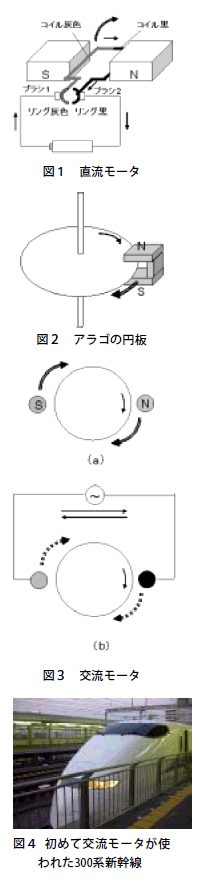 前回の『かたつむり』に、東海道線の新型車両に交流モータが使われていると書いた。
それを見た運営委員の先生から「東海道線は直流区間なのに交流モータなの?」と質問を受けた。
もともと直流モータを使うため、直流の架線が引かれたのに、どうして交流モータ?と思うのは当然だ。
でも、間違いなく新型車両には交流モータが使われている。
前回の『かたつむり』に、東海道線の新型車両に交流モータが使われていると書いた。
それを見た運営委員の先生から「東海道線は直流区間なのに交流モータなの?」と質問を受けた。
もともと直流モータを使うため、直流の架線が引かれたのに、どうして交流モータ?と思うのは当然だ。
でも、間違いなく新型車両には交流モータが使われている。その理由は2つ。1つは交流モータの構造が単純で壊れにいため。 もう1つは交流モータと使うことで電気を有効に使えるため。 直流モータでは電車の動き出しと停止時には半分の電気をムダにしている。 これに対し交流モータでは90%以上を有効活用できる。 今回は、2種類のモータの違いについて述べる。 まず、直流モータの構造から。直流モータの構造は、図1のようになっている。 SとNの磁石の中にコイル(電線を巻いたもの)が置かれている。 コイルには半分に切れたリングがつながっていて、これが2個のブラシと呼ばれている物と接している。 このブラシは固定されていて、コイルはブラシに接しながら回転する。 図1ではブラシ1がリング灰色、ブラシ2がリング黒に接していて、 ブラシ1→リング灰色→コイル灰色→コイル黒→リング黒→ブラシ2と電気が流れる。 コイル(電線)に電気が流れると磁石の性質を持つため、コイルは上に向かって回転する。 半分以上回転すると、今度はブラシ1→リング黒→コイル黒→コイル灰色→リング灰色→ブラシ2と電気が流れ、 黒のコイルが上向きの力を受けて回転する。 ブラシが無く電線が電池につながっているだけだと、コイルは真上で止まってしまう。 ブラシのおかげで、コイルを流れる電気の向きが次々と変わり、直流モータは回転する。 次に交流モータ。交流モータを知るためには「アラゴの円板」を理解するとわかりやすい。 図2のように、中央に回転軸のある金属円板(アルミなど)に磁石を近づけ、磁石を動かすとどうなるだろう? 円板は止まったままだろうか、磁石と同じ方向に動くのだろうか、それとも反対の方向に動くのだろうか。 答えは“同じ方向に動く”だ。電気が流れると磁石の性質を示すのとは反対に、磁石が動くと電気が流れる。 アラゴの円板では、磁石の動きにより円板の中で電気の流れが発生する。 電気の流れは磁石の性質を示すから、磁石に引かれて動く。 このことから、図3(a)のようにNとSの磁石を周囲で廻せば、磁石に引かれて円板が回転することがわかる。 ここまで理解できれば、 図3(b)のように磁石にの代わりに電気を流して磁石の性質を持つコイルを使っても良いと想像ができる。 もう一歩進めて、コイルへの電気の流れを右左に入れ替えだらどうなるだろう。 電気の流れの向きで磁石の方向が決まるから、NとS、SとNが切り替わっている。 円板にとっては周磁石が回転しているように感じられ、これに引かれるように回転する。 ところで、前回の交流を思い出して欲しい。交流では、プラスとマイナスが交互に繰り返されている。 図3(b)のコイルにつなげば、電気は左右に流れ、円板を回転させることが出来る! 直流モータではブラシが電気の流れを交互に入れ替えているのに対し、 交流モータでは電気のプラスとマイナスが交互に入れ替わっているからだ。 このように直流モータではブラシやリングが必要で、 電車に使うモータともなればブラシやリングも相当な大きさで重い。 しかも、ブラシはいつもリングと接していなければならないから、直流モータの電車では定期的な検査が必要。 交流モータではこれらが無いから構造が単純で軽く安い。しかも壊れにくくブラシの検査も不要だ。 このため、電車のモータは15年程前から次々と交流モータ方式に置き換わっている。 交流モータは新幹線にも取り入れられた。 東海道新幹線では「のぞみ」(図4)に交流モータの車両が導入され、 時速300kmの運転ができるようになった。 その後に作られた新型車両はすべて交流モータが採用され、 東京と大阪間では直流モータの新幹線は数年前に姿を消した。 さて、次回の『かたつむり』では、交流モータが電気をムダにしないしくみについて紹介する。 |
 戻る
戻る