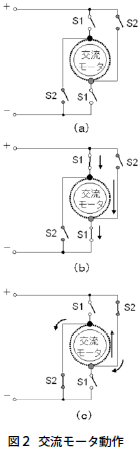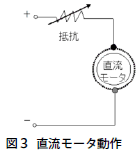このレポートは、かたつむりNo.281[2006(平成18)2.12(Sun.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| ありがとう!110系東海道線(湘南電車)3 | ||
| 運営委員 高 木 茂 行 | ||
 1月8日(日)の国立科学館の見学では、
行きも帰りも東海道線は古い113系の車両(湘南電車)ではなかった(図1)。
新型車両E231系への置き換えが急速に進み、古い車両はどんどん減っている。
東海道線を走る113系電車の姿が見られるのは、残りあとわずかになっている。
この電車が好きな人は、早めに乗っておくことをおすすめする。
1月8日(日)の国立科学館の見学では、
行きも帰りも東海道線は古い113系の車両(湘南電車)ではなかった(図1)。
新型車両E231系への置き換えが急速に進み、古い車両はどんどん減っている。
東海道線を走る113系電車の姿が見られるのは、残りあとわずかになっている。
この電車が好きな人は、早めに乗っておくことをおすすめする。さて、前回と前々回の「かたつむり」で、直流モータと交流モータの違いを書いてきた。 直流モータはブラシを使ってコイルに流れる電流を切り替えているのに対し、 交流モータは時間とともに流れる向きの変わる電気を利用して、モータを回転させている。 でも、東海道線の架線(カセン)には直流がきている。どうすれば、直流から交流が作れるのだろう。
一方、直流モータでは、図3に示すようにモータに抵抗(テイコウ 電気工作で使う抵抗の大きい物) をつなぎ、この抵抗の値を変えることでモータの回転数を変えている。 図の中でぎざぎざした記号が抵抗で、矢印は抵抗の値が変わることを示している。 抵抗が大きいほど電気の流れは少ないので、動き出すときは抵抗の値を大きくしておき、 抵抗を小さくしていき回転数を高める。 直流モータでは、電車が動き始める時、抵抗にも電気を流している。 抵抗に流れた電気は熱となって使われてしまうので、電気がムダになる。 交流モータでは、スイッチの入り切りでモータを回しているので、ムダな電気は交流モータに流さない。 ほとんどの電気がモータの回転に使われる。モータが回り始める時、 直流モータでは50%以上の電気がムダになることもあるのに対し、 交流モータではムダになる電気は10%以下になる。1日に何回も行き来する電車にとって、 この差はとても大きい。2回目の原稿で書いたように交流モータは仕組みも簡単で軽く、 さらに電気を有効に使っている。そして、交流モータでのスイッチ動作が可能となったのは、 半導体の性能が格段に向上したためだ。 今では新しく作られる電車のほとんどが交流モータになっている。 東海道線も交流モータを使った新しいE231系に次々と変わっている。 最近になってJRの駅には、新型車両をアピールするポスターが貼られた。 今年3月のダイヤ改正ですべての車両が新型に置き換わると書かれてある。 古い113系の車両が東海道線を走るのは、いよいよ秒読み段階に入ってきた。 新しい車両の良さは理解できるが、その一方で古い車両は数十年の長きに渡り我々のために働き続けた。 平日は東京方面に向かう通勤客を乗せ、週末には熱海や箱根、そして湘南方面への観光客をのせて毎日続けた。 その勇姿と活躍には、惜しみない拍手を送りたい。「ありがとう110系東海道線!」 |
||
|
||
|
−終わり− |
 戻る
戻る