このレポートは、かたつむりNo.293[2006(平成18)12.22(Sat.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| 10月活動を振り返って(1) | ||||||
| −名前の由来に感動 秋の野草− | ||||||
| 運営委員 高 木 茂 行 | ||||||
その1週間前の10月8日には運営委員が集まって同じコースの下見をした。 高山先生はデジカメで写真をとり、「泉の森付近のフォトビンゴ」を作られた。 高木もこれに参加し、高山先生に教えていただきながら写真を撮った。 その時のメモと写真を持って図書館に行き、印象に残った植物を調べた1-4)。 今回は名前の由来が面白い植物についてまとめた。 泉の森に入ってすぐのところ「森のはらっぱ」付近にあったのが“ウバユリ(姥ゆり)”(図1)。 実がつく頃には葉が落ちるので、 それを姥(うば)の歯が落ちるのに例えて“ウバユリ”と名づけられている。 実際には、葉の落ちたもの落ちないものが混在していた。 落ちたものは長く延びた茎の上に実だけがあり、 その姿が印象的だった。ところで、この“ウバユリ”の花は何色だろう? 「日本の野草(夏)」を見ると白い“ウバユリ”花の写真が載っている。 「森のはらっぱ」から少し歩き、あじさいの道が太い道と合流するところには “ミズヒキ(水引)”が生えていた(図2)。 高山先生からは『上側が赤、下側が白で、これを紅白の水引にたとえています』と教えていただいた。 確かに表から見れば赤く、裏側からみると白い。 下見の時は納得したのだが、団員から『紅白の“みずひき”ってなに』と聞かれ、 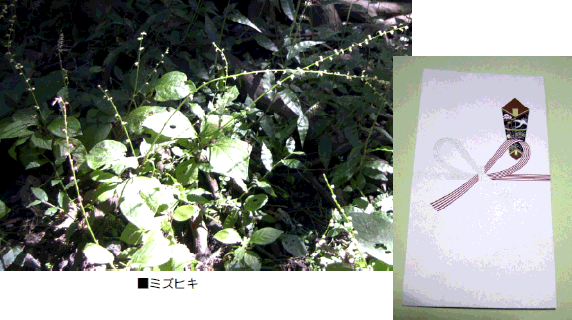 「お祝いの時の封筒にある赤と白ののし」と答えたのだが十分には納得がいかなかったようだ。
そこで、図3に水引の写真を載せた。これで納得していただけるだろうか?
「お祝いの時の封筒にある赤と白ののし」と答えたのだが十分には納得がいかなかったようだ。
そこで、図3に水引の写真を載せた。これで納得していただけるだろうか?
せせらぎ広場に咲いていた小さな花は“ゲンノショウコ”(図5)。 土から上の部分を天日で乾燥させて煮て(煎じて)飲むと、 すぐに効くことから『現(げん)の証拠』の名がついている。 漢字では書くと、『現証拠』または『現の証拠』。 「日本の野草秋」で調べると、花の色は東日本で白色が多く、西日本では紅紫色が多いと書かれている。 泉の森で咲いていたのは、この本の通り白い花だった。 薬としての使いからなどをインターネットで調べると5)、次のように書かれていた。 『ゲンノショウコは、飲みすぎても便秘・下痢などの副作用がなく、優れた健胃調整剤といえます。 食中り(しょくあたり)、下痢、慢性の胃腸病、便秘
今回紹介した野草は、名前が植物の特徴を上手く示している。 これを理解しながら先日のフォトビンゴをもう一度見直せば、 植物の名前がしっかりと覚えられるだろう。 参考文献
|
 戻る
戻る


