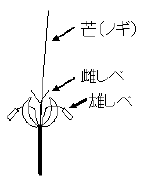このレポートは、かたつむりNo.294[2007(平成19)1.14(Sun.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| 10月活動を振り返って(2) | |||||||||||
| −秋の野原を彩るイネ科の植物− | |||||||||||
| 運営委員 高 木 茂 行 | |||||||||||
|
今回は、10月活動の1週間前(10月8日)に下見に行った時のまとめ(2)だ。
実りの秋というように多くの植物が秋には実を結ぶ。
その中でも、実りの秋にふさわしいのはお米(稲)だろう。
黄土色に輝く稲の穂が一面に広がる田圃(タンボ)の姿は、誰の心にも懐かしさを感じさせる。
そして稲が実りを迎えるように、野原のイネ科の植物も秋には輝きを増す。 さて、イネ科の植物とはどんな植物だろうか? 稲の特徴を考えてみよう1-4)。 稲は綺麗な花はつけないが種は残す。綺麗な花の部分、すなわち花びらはタンポポでは黄色、 桜はピンクというように、いわゆる花の部分だ。これに対して稲には花びらがなくとても地味だ。 この花が実を結び種、いわゆるお米を残す。また、稲の茎は中が空っぽ(空洞)になっている。 稲の茎が枯れたワラの中が空っぽだったことを思い出してもらえばよい。 少し難しい説明が続いたが、10月活動で見たイネ科の植物の名前を列挙してみよう。 そうすれは、これらの特徴が共通していることを納得できるだろう。 エノコログサ、ススキ、オギ、ジュズダマ、カゼクサ、チカラチバ・・・だ。 どれも綺麗な花は咲かないし、細長く延びた茎の先に、花あるいは実の塊(カタマリ)がついている。 これらの植物を、順番に見てみよう1-4)。
次に森の原っぱに生えていたのがススキ(図2)。 その名前は、スクスク立つ木に由来、 あるいはスレスレにくっつきあって隙間が薄いことに由来しているといわれている。 秋を代表する草で、箱根の仙石原の一面に広がるススキの姿は見事だ。 ススキに似ているがオギ(図3)。オギはススキより湿り気のあるところを好む。 10月活動では、実に芒(ノギ)があるのがススキ、ノギがないのがオギと説明があった。 ノギって何という質問を何人かの団員から聞かれたので、図4にノギの図を付けた。 花の中央から長く延びたヒゲのようなものがノギだ。これはイネの花にもある。 ぜひ一度、ススキ、オギ、イネを見て確かめてみて欲しい。
順番に挙げていくと、イネ科の植物が秋の野原に彩を添えているのが分かる。 イネ科の植物の特徴をつかんでからエノコログサ、ススキ、オギ、ジュズダマ、カゼクサ、 チカラシバを眺めれば、これらの植物を名前も覚えやすいだろう。 (終り)
|
 戻る
戻る