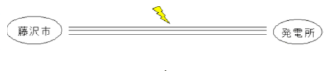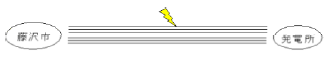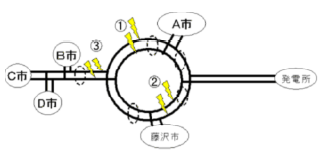このレポートは、かたつむりNo.299[2007(平成19)5.20(Sun.)]に掲載されました
 戻る
戻る
| 首都圏停電(3) | ||||||||
| -インターネットにも似た電力のネットワーク- | ||||||||
| 運営委員 高 木 茂 行 | ||||||||
僕らの住んでいる藤沢に遠く離れた発電所から電気を運ぶことを考えてみよう。 一番簡単な方法は、図1のように発電所と藤沢市を一組の送電線でつなぐことだ。 図1が3本の線になっているのは、首都圏停電(1)で書いた三相交流を表している。 ところで、発電所の多くは、水力発電のダムのように首都圏からは100km以上も離れている。 それだけ長い距離をつなぐと、どこかで雷が落ちたり、強風で送電線が切れたりし、 停電の頻度が高くなる。 これを減らす方法として、図2のように送電線を二重にすることが考えられる。 実際には鉄塔の両側に2組の送電線を張ることで確実に送電できるようにしている。 どちらか一方が切れても、残った送電線で電気を送ることが出来るわけだ。 もっと停電を少なくするにはどうしたら良いだろうか。 その答えが図3で、送電線をドーナツ状(環状)に張り巡らす方法だ。 図1、2では三相交流をそのまま3本で書いたが、複雑になるため、 図3では三本をまとめて太い線で書いている。 この方式では、①が雷や事故で切断されても、右回りで電気を藤沢市に送ることが出来る。 同様に②で事故が起きたら、左回り周りで電気を送ることが出来る。 パソコンのインターネットは、通信のための線が複雑につながり、 どこが切れてもつながるようになっている。 送電線も同じような考えが取り入れられていて、電力のネットワークと呼ばれている。 ところで、①で事故が起きたとき、その影響が他に及ばないようするためには、 電気を止めて他への影響が無いようにする(遮断)必要がある。 このための施設が、中継所であったり変電所であったりする1)。 図3で点線の楕円がこの施設に相当する。②に雷が落ちたとき、②の両側で電気を遮断すれば、 停電は藤沢市だけにとどまり、他は通常通りに電気が使える。図3は藤沢市内の変電所の写真だ。 このように電線が張り巡らされた設備を皆さんも見たことがあるだろう。 ところで、すべての地域を直接に環状の送電線につなぐと接続点が多くなり、 遮断するための施設も多くなる。 そこで、図3のB市、C市、D市のように環状の送電線から放射状に送電することになる。 この方式では、③に雷が落ちると③近くの中継所あるいは変電所で電気を遮断するため、 B市、C市、D市には電気が送電されなくなる。 放射状に伸びる送電線の根元、すなわち環状の送電線近くで事故が起きると、 停電する地域は大きくなる。 昨年8月14日のクレーン船事故は、 環状線近くで送電線が切れた典型的なパターンだった2)。 また、クレーン船は鉄塔に張られた送電線を両側とも切断してしまった。 図2で示した被害に備えるもう一組の送電線も切断してしまった。 こうして、140万戸もが停電する事故となった。 8月14日の事故は、運悪く電力のネットワークの弱いところを直撃した。 しかし、実際には電力のネットワークのおかげで、ほとんど停電することなく電気は送られてきている。 電気を効率よく安全に送るため、三相交流、高い送電線、 電力のネットワークなど普段は気付かない工夫がこらされている。 われわれを楽しませてくれる美しい夜景(図4)も、こうして送られてきた電気のおかげだ。 (終り)
|
 戻る
戻る